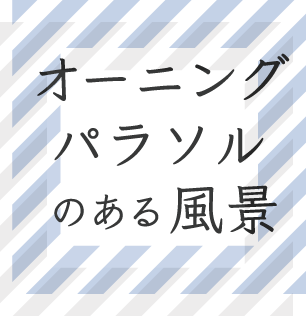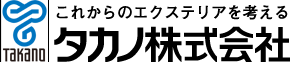日よけの活用で“歩きたくなる街”を実現!ウォーカブルなまちづくりの事例と、成功に導くポイントを徹底解説
近年、歩行者が快適に過ごせる「ウォーカブルなまちづくり」が注目を集めています。
歩道の整備やストリートファニチャー、日よけ製品を活用することで、歩行者の利便性が向上し、地域に賑わいを生み出す効果が期待できます。
本コラムでは、ウォーカブルなまちづくりの事例と成功のポイント、さらにウォーカブルなまちづくりを支援する日よけ製品もご紹介します。
読めばきっと「歩きたくなるまちづくり」のヒントが得られるはずです。

1. ウォーカブルなエリアとは?その定義と重要性
ウォーカブルエリアの基本的な概念
ウォーカブルエリアとは、歩行者が快適かつ安全に歩ける空間のことを指します。広い歩道や緑地、ベンチ、オーニングやパラソルなどの日よけ設備が整備された環境がその特徴です。
日本でも、歩行者利便増進道路 通称ほこみち制度などを活用した取り組みが進んでいます。
また、車両の通行を制限し、歩行者空間を優先することで、都市のにぎわいや交流が生まれやすくなる特徴もあります。

ほこみち制度の概要や活用例をご紹介しています
歩きたくなる街の条件とは?
歩行者が安心して移動できる安全な歩道や、日よけのある休憩スペースといった設備が充実しているかが重要なポイントです。さらに、道路や街路が快適に整備され、緑地や広場が豊富で、イベントや名所が多い街は、人々が「歩く楽しみ」を実感できます。このような環境整備がウォーカブルなまちづくりの基盤となります。

有楽町のオフィス街では、ストリートファニチャーや樹木、パラソルを活用し、歩行者がくつろげる空間を創り出しています
ウォーカブルなまちづくりによる地域活性化のメリット
ウォーカブルなまちづくりを実現すると、歩行者の増加に伴う人々の自然な交流や地域経済の活性化が期待できます。また、「歩きたい」と感じるようになることで新たな店舗やサービスの需要が生まれ、付加価値を創出しやすくなります。さらに、歩行エリア拡大による交通事故対策や、車両利用の減少は二酸化炭素の排出量削減や住民の健康促進にも寄与し、サステナブルな都市再生につながります。
2. 海外と日本のウォーカブルなまちづくりの事例
海外の先進事例:アメリカ ニューヨーク市
ウォーカブルなまちづくりにおいて、欧米諸国は先進的な取り組みを行っています。
アメリカでは、車道を歩道に変えたり、歩行者中心の屋外空間の活用を進めたりするなど、ウォーカブルなまちづくりが加速しています。
ニューヨーク市では、新型コロナウイルス感染拡大以降、路面の飲食店に歩道や車道を使って座席を設置する特例制度を導入し、占用料も免除されています。

アメリカ ニューヨーク マンハッタンのレストラン屋外ダイニング(2020年コロナ禍)
参考:国土交通省「ウォーカブルなまちづくりの海外事例紹介」
日本国内のウォーカブルなまちづくり事例
国内でもいくつかの都市でウォーカブルなまちづくりが成果を挙げ、さらに年々「歩きたくなるまちづくり」に向けた社会実験を行う地域・自治体が増えています。
①東京都目黒区 自由が丘 九品仏川緑道(くほんぶつがわりょくどう)
自由が丘駅南側の東西に延びる九品仏川緑道では、昭和48年から一時的な歩行者天国を実施していました。しかし、道路が狭く歩行者と自動車の交錯が起こるなどの課題が挙がりました。そこで、歩行者優先ゾーンの設定や道路のバリアフリー整備などの社会実験を実施。また、「自由が丘スイーツフェスタ」といったイベントを実施したり、ベンチを配置して駐輪対策を行ったりと、官民連携のもとで継続的な沿道まちづくりを進め、歩行環境を改善し、にぎわいを創出しています。

ウォーカブルなまちづくりの先進事例 東京都目黒区 自由が丘の「九品仏川緑道」
参考:東京都都市整備局「歩行者中心の道路空間の 活用マニュアル - 8. 歩行者空間創出の先進事例」
②長野県飯田市 りんご並木
中心市街地の活性化を目的に、路地空間を活かしたオープンテラスなどを整備し、人々が気軽に集える交流空間づくりに取り組んでいます。
2024年には「憩いや集いのステージとなるりんご並木」の実現に向けて交通規制を伴う社会実験を実施。リンゴ並木沿いの車道を一時的に歩行者天国にし、路面飲食店のオープンテラスやフリースペースの設置、近隣動物園の動物のお散歩イベント、出張図書館といったさまざまな活用が試されました。
 歩道やベンチが設けられた飯田市のリンゴ並木。両サイドに車道が通っている
歩道やベンチが設けられた飯田市のリンゴ並木。両サイドに車道が通っている
3. 成功させるためのポイント
事例から学ぶ共通点と成功の秘訣
日本国内外のウォーカブルなまちづくり事例では、歩道や公共空間を「人々が安心して集い、過ごせる場所」に再設計する点が共通しています。緑地や日よけ、テーブルの設置、舗装デザインを工夫して、歩行者中心の空間を創出していることが特徴です。
さらに、住民の意見を反映した社会実験や共同作業を通じて、地域の満足度や都市全体の魅力を高める取り組みが進められています。

社会実験や住民参加による歩行者中心のデザインプロセス
ウォーカブルなまちづくりにおいて、車両通行制限や空間配置を一時的に変更して実際に検証する社会実験は、地域課題や改善点を明らかにする重要な手段です。
また、住民や地元事業者の声を反映したデザインプロセスは、街への愛着や「歩きたくなる」空間づくりをさらに促進し、ウォーカブルなまちづくりの質を高める鍵となります。
緑地創出と公共交通インフラの連携による快適な都市空間
緑地や街路樹などの自然要素を活用し、木陰やオーニング製品などの日よけを配置することは、夏場でも快適に歩ける環境づくりに欠かせません。加えて、駅やバス停などの公共交通機関との接続を考慮した歩行者専用道路や、休憩スペースを整備することで、移動と滞在の両面でまちの魅力と利便性を向上させます。

4. ウォーカブルなまちづくりに活用できる日よけアイテム
日よけの重要性
歩行者が快適に過ごせるよう、特に日差しの強い季節にはオーニングやパラソルなどの日よけを整備することが重要です。適切な日よけを設置することで居心地の良い歩道や広場が実現し、歩行者の利便性を高めるだけでなく、滞留スペースとしての価値を高める役割を担います。
日よけ付き屋外用テーブル
日よけ付き屋外用テーブルは、道路空間や公園、広場などに設置することで、地域住民や来訪者のコミュニティの場となるのがポイント。急な天候変化にも対応しやすく、キャスター付きの製品なら移動や配置転換が容易です。
タカノが扱う製品例:
- 開かれたコミュニケーションの空間を提供する日除け付き移動式テーブル
- テーブルの高さを2段階に調節可能
- 天候や時間帯に合わせて取り外し可能なシェード
- キャスター付きで移動が容易
移動式パラソル
パラソルは、ウォーカブルなまちづくりにおいて非常に重要なアイテムです。カフェテラスやベンチ周辺の休憩スペースなどに設置することで、歩行者が快適に滞在できる空間を提供します。
移設させやすい移動式パラソルは設置する側にとっても利便性の高いアイテムです。
タカノが扱う製品例:
- カフェテラスなどに最適な片持ち大型パラソル
- 安全性を考慮した突風時の転倒・破損を防ぐオリジナル機能搭載
- 腐食に強いアルミ製の支柱
- 固定方法が選べ、キャスターを付けた移動式仕様が選択可能
移動式オーニング
オーニングには、建物と一体化させるタイプと、独立して日よけを作る自立型オーニングがあります。移動が簡単な自立型オーニングは広場などの広い空間で大きな日陰を作ることができ、イベントやレイアウト変更の際に移設が容易です。
オーニングは、商店街やカフェのある街路といった場所の特性に合わせて設置することで、強い日差しや雨から来訪者を守り、快適な空間を提供できます。
タカノが扱う製品例:
設置・解体が簡単にできるオーニング
イベントに合わせた素早い設置や撤去ができるオーニングは、ウォーカブルなまちづくりを支える柔軟な日よけアイテムです。季節や天候に応じて快適な空間を創出し、歩きたくなる街の賑わいを促進します。
タカノが扱う製品例:
まとめ
ウォーカブルなまちづくりは、車中心から歩行者主体へと転換する都市再生の重要な取り組みです。日よけや屋外ファニチャーを活用し、人が安心して歩き、滞在できる空間を整えることで、より地域の魅力や経済活動の活性化につながります。今後は、公共交通との連携や社会実験を通じて成功事例を広げ、多様なニーズに応えるまちなかのウォーカブルエリアの展開を進めることが求められます。
日よけアイテムや屋外ファニチャーに関するご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。自治体や商店街、路面飲食店の皆さまのウォーカブルなまちづくりを、タカノの製品で力強くサポートいたします。
また、実際にオーニングやパラソルが見られる展示場が、東京都と長野県にございます。 ぜひ、実物をお確かめください。ご来場お待ちしております。
ウォーカブルなまちづくり・日よけの設置について よくあるご質問
ここでは、ウォーカブルなまちづくりや日よけの設置について、よく寄せられる質問にお答えします。
Q1ウォーカブルなまちづくりは具体的に何をすれば実現できるのでしょうか?
A1ウォーカブルなまちづくりを進めるには、まず広い歩道や安全な通路の確保、バリアフリーの導入など、歩行者が安心して移動できる空間を整備することが重要です。さらに、公園や広場を設けるほか、パラソルやオーニングといった日よけ設備を配置し、くつろぎやすい休憩スペースを作ります。住民や地元事業者を交えた社会実験を行いながら、徐々にインフラを整えると効果的です。
Q2日よけ製品はどのように選べばいいのでしょうか?
A2設置場所の広さ、想定される利用人数や用途に合わせて選ぶのがポイントです。例えば、キャスター付きのパラソルやオーニングは移動や撤去が容易なので、イベントや季節によってレイアウトを変更したいエリアに適しています。また、風や雨、突風対策に優れた安全設計の製品を選ぶと、運営者の手間やトラブルのリスクが軽減されます。
Q3公共エリアに大きなオーニングやパラソルを設置するときに、行政への申請は必要ですか?
A3歩行者利便増進道路(ほこみち制度)など、道路空間を活用する場合には、行政による許可や申請が必要となるケースがあります。自治体や管轄部署によって申請方法が異なるため、事前に確認した上で書類を整え、適切な手続きに沿って設置を進めることが大切です。
Q4ウォーカブルな空間づくりで住民の満足度を高めるには、どのような工夫が効果的ですか?
A4住民の声を反映した社会実験や、街づくりに参加できるワークショップを開催し、アイデアを募るアプローチが有効です。歩道・屋外スペースにはベンチや日よけ、植栽などをバランスよく配置して、滞在・交流を楽しめる環境を整えます。市民が積極的に意見を出し合うことで愛着が生まれ、継続的なまちの発展につながります。
Q5日よけ製品のメンテナンスや保管はどのように行えばいいですか?
A5製品によって管理方法は異なりますが、多くの場合は定期的に布地を点検し、汚れや傷みを確認することが大切です。可動部分の錆や劣化を防ぐため、定期的に潤滑油を注すなどのメンテナンスも必要となる場合があります。撤去やオフシーズンに保管する際は、日よけ部分をしっかり乾かしてから折りたたみ、湿気の少ない場所に保管すると製品寿命を延ばせます。
▼オーニングやパラソルのお手入れ方法の詳細はこちらをご覧ください
「オーニングとパラソルのメンテナンス術 ~長く安全に使用するためのお手入れ方法~」